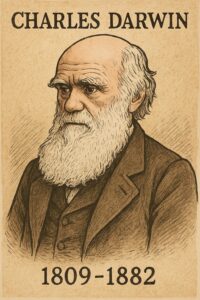
発達障害だと思われる有名人1
チャールズ・ダーウィン(1809–1882)には、現代の視点から見ると自閉スペクトラム症(ASD)や限局性学習障害(LD)の傾向があったのではないかと推測される逸話がいくつかあります。もちろん医学的診断ではなく、行動特性や記録からの推察です。
ダーウィンは「社会的な空気を読むのが苦手」「論理的で合理的」「特定分野に異常な集中力」など、高機能自閉症(アスペルガー症候群)に近い特徴を持っていたとされています。
また、限局性学習障害(LD)の傾向として、言語や詩作の困難さをもっていたと言われています。(参考:精神医療従事者によるサイコセラピー研究所「発達障害が天才といわれる理由とは?実際はどうなの?」[2025年7月26日参照])
チャールズ・ダーウィンとは
チャールズ・ダーウィン(1809–1882)は、イギリスの自然科学者・地質学者であり、進化論の父として知られています。若い頃は医師や牧師を目指すも、自然観察への情熱から博物学に傾倒。1831年から約5年間、海軍測量船ビーグル号に乗船し、南米やガラパゴス諸島などを巡る航海で多様な動植物を観察・収集しました。この経験が、後の「自然選択による進化」という理論の着想につながります。
1859年に発表した代表作『種の起源』では、生物が環境に適応しながら世代を経て変化することを科学的に説明し、宗教的創造説に一石を投じました。
ダーウィンの具体的な逸話と行動
幼少期の孤立と自然への没頭
ダーウィンは8歳のときに母親を亡くし、家庭内で深い喪失感を抱えながら育ちました。この出来事は彼の内面に大きな影響を与え、学校生活でも周囲との関係に馴染めず、教師からは「平凡な少年」と評価されることもありました。そんな中、彼は自然界に強い関心を示し、昆虫や鉱物の収集に没頭するようになります。
特に印象的なのは、兄と一緒に化学実験を行っていたエピソードです。家の物置を実験室に改造し、怪しげな気体や化合物を作っては観察を繰り返していたため、周囲から「ガス」というあだ名で呼ばれていたほど。こうした逸話は、彼が幼少期から「観察」と「分類」に強いこだわりを持っていたことを物語っています。
結婚の判断を論理的に下したエピソード
ダーウィンは結婚についても、感情ではなく論理的な思考で判断したことで知られています。1838年、彼はノートに「結婚するべきか、しないべきか」という二項対立のメモを書き、メリットとデメリットを列挙しました。
- メリットには「老後の伴侶」「友人」「犬よりはまし」といった項目が並び、
- デメリットには「本のための資金が減る」「時間の浪費」「自由の喪失」などが記されていました。
このように、人生の重大な選択をまるで研究テーマのように分析した彼の姿勢は、自然選択説の構築にも通じる「合理性と検証主義」の現れです。最終的には、従姉妹エマ・ウェッジウッドにプロポーズし、結婚生活を通じて10人の子どもをもうけましたが、その判断は感情よりも「長期的な生活設計」に基づいていたのです。
ルーティンへの強い執着
散歩・研究・妻とのバックギャモン・食事などを毎日同じ順序で繰り返し、生活リズムが崩れると体調を崩すほどでした。
- 毎日の散歩ルートを厳密に管理 同じ庭道を何周歩いたかで思考の深さを測るなど、散歩は彼の“動く瞑想”でした。
- 読書と記録の時間を固定化 科学書だけでなく宗教・哲学・歴史にも広く触れ、思索の幅を広げる読書習慣を持っていました。
- 思考の持続を重視 「私は最も賢い人間ではない。ただ、長く考えることができた」という言葉に象徴されるように、焦らず何十年も理論を練り続ける姿勢がありました。(参考:モジ―/MOZZY/ 人間の「行動変容」を考えるNOTE「偉人たちの特筆すべき習慣:知性の源泉を探る第5章:チャールズ・ダーウィンの「観察と思索のルーティン」」[2025年7月26日参照])
極端なこだわりと観察癖
特定の生物(フジツボ、ミミズなど)に異常なまでの関心を持ち、毎日同じ時間に観察。息子が「お父さんは何時にフジツボを観察するの?」と聞かれるほど日常化していました。
- 幼少期から自然観察に没頭 昆虫採集や鉱物収集を好み、兄と化学実験を行うなど、観察と記録が生活の一部でした。
- ビーグル号航海での徹底したフィールドノート 南米やガラパゴス諸島での動植物の記録は、後の進化論の土台に。特にマネシツグミやゾウガメの微細な違いに注目した姿勢は、観察眼の鋭さを物語っています。
- 自宅の庭でも日々観察を継続 帰国後も植物や昆虫の変化を記録し続け、ミミズの土壌への影響など身近なテーマにも科学的関心を向けました。
子どもの発達観察への関心
自身の長男ウィリアムの乳児期を詳細に観察し、行動・表情・言語理解などを記録。これは後の発達心理学に影響を与えました。(参考:日本心理学会「心理学ってなんだろう サトウ タツヤ」[2025年7月26日参照])
- 長男ウィリアムの乳児期を科学的に観察 生後7日から2歳までの行動・表情・言語理解などを詳細に記録し、1877年に『Mind』誌に「乳児の略伝」を発表しました。
- 言語理解の早期獲得に注目 初語が出る前から言語を理解する様子を記録し、「下等動物も人間の言葉を理解できる」と結論づけました。
- 発達心理学の先駆者としての影響 ダーウィンの観察は、後のスタンレー・ホールやプライヤーらによる児童研究運動(Child Study Movement)に影響を与え、発達心理学の誕生に貢献しました。
言語学習の困難さ
詩作が苦手で、学校の課題では友人に助けてもらっていました。外国語の習得も一生できなかったとされています。
ダーウィンは、詩作や文学的表現に対して強い苦手意識を持っていたことで知られています。ケンブリッジ大学時代には、神学を学ぶ傍らで詩の課題に取り組む必要がありましたが、自分ではうまく書けず、友人に助けてもらっていたという逸話があります。彼自身も「詩を読むと頭が痛くなる」と語っており、文学的な言語処理に対して明確な抵抗感があったようです。
また、外国語の習得にも大きな困難を感じていたことが記録されています。エディンバラ大学では医学を学ぶ傍ら、ラテン語やギリシャ語などの古典語に触れる機会がありましたが、語彙の暗記や文法の理解に苦しみ、学位取得を断念する一因にもなったとされています。ケンブリッジ大学でも神学の一環として言語学習が求められましたが、ダーウィンは「外国語は一生習得できなかった」と回想しています。
科学的成果との対比
興味深いのは、ダーウィンが言語的な困難を抱えながらも、科学的な文章では極めて明晰な論理展開を行っていたことです。『種の起源』や『人間の由来』などの著作は、複雑な理論を平易な言葉で説明する力に満ちており、これは口語的・詩的な言語とは異なる「説明言語」に特化した能力があったことを示唆しています。
つまり、ダーウィンは言語の「芸術的・感性的な側面」には苦手意識があったものの、「論理的・説明的な側面」では高い能力を発揮していたという、言語能力の偏りが見られる人物だったのです。