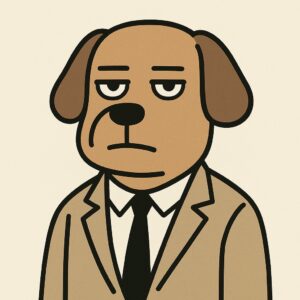
以前に、「ヘラヘラ笑ってしまう」で紹介した通り、発達の人の中には、場にそぐわない笑い方をしてしまったり、自分の苦しみから逃れるために笑ってしまったりするタイプの人がいます。
それとは別に、(本人にとっては)ショックな出来事が起こったときや、どう反応したらいいのかわからない状況のときに、顔が能面のように固まってしまい、無表情になってしまうタイプの人がいます。
感情処理が苦手
発達障害(神経発達症)の人の中には、自分の感情を処理するのが苦手な人が多くいらっしゃいます。特に苦手なこととしては、
- 本人にとって想定外のことが起こったとき
- 並列的に状況を処理しないといけないとき
- 強い喜怒哀楽の感情が出たとき
- 自分の感情を認知することが苦手なタイプの人
などです。
このようなときに、本人が自覚しているしていないかはともかく、第3者の目からみると顔に表情がなくなって固まってしまうことが多くあります。
頭の処理と心の処理にズレが生じる
比較的高知能の人に多いのですが、頭の回転そのものは早いのに、感情面での処理が苦手だったりするとこのような状況になってしまうことがあります。
周りの人がよく勘違いをしてしまうのですが、頭(認知能力)がいいからといって、感情処理が早いというわけではありません。「この子頭はいいはずなのに、なんでグズグズしているんやろう」と思ってしまいますが、「頭ではわかっていても動けない」という状況になっているのです。例えて言うと、頭のコンピューターが最新式のCPUでとっくに処理が終わっている(認知できている)のにもかかわらず、心のコンピューターが30年前のCPUで、まだ処理が終わっていないので動けない、という状況になっていることが多いのです。
このようなタイプの人の場合、頭ではその場で状況を理解しているが、本人の心が納得して動き出せるようになるまで、数日~1周間もかかる人がいます。自分の感情を認知するのが苦手な人の場合は、数週間後に「あのとき~できなかった」とぐちを言ったり、数ヶ月後に感情を爆発させたりします。
心の処理が苦手で無表情になる、と聞くと、多くの人はASDの人を思い浮かべるかもしれませんが、ADHDと診断されている人でも、顔が無表情になってしまう人がいらっしゃったので、ASDだから、ADHDだから、と決めつけるのはよくないです。
場面緘黙
発達障害を持つ人の中には、場面緘黙(ばめんかんもく)になりやすい傾向があります。これは特定の場面や状況で話すことが難しくなる状態で、特に自閉スペクトラム症(ASD)や社交不安が強い人によく見られます。家庭では会話ができるのに、学校や職場などでは一言も発せず、周囲には「無口な人」「無愛想」と誤解されがちです。場面緘黙は本人の意思で黙っているわけではなく、心理的緊張や不安によって「話したくても話せない」状態に陥っているのが特徴です。このため、単なる「人見知り」として片付けられることなく、その背後にある発達特性への理解が必要です。
場面緘黙を解消するには、まず本人の不安を減らし、安心して声を出せる環境づくりが重要です。無理に話すことを強要せず、「話さなくてもここにいていい」と感じられる場を用意することが第一歩です。また、言語以外のコミュニケーション手段(ジェスチャー、カード、筆談など)を尊重しつつ、自己表現への成功体験を積み重ねていくことが支援の鍵となります。
学校などの集団生活の場では、信頼できる大人(担任や支援員)とペアを組み、小グループでの活動から始めて、段階的に社会的なやり取りの範囲を広げていく方法が有効です。例えば、あいさつカードを使って「声に出さずに気持ちを伝える」練習を通じて、自信と安心感を育てていくことができます。
加えて、心理士などの専門家によるカウンセリングや、認知行動療法的アプローチも有効とされています。不安のコントロール方法を学んだり、「話すこと」に対する認知の再構築を図ることで、徐々に話せる場面が増える可能性が高まります。
大切なのは、「話せない」ことを責めたり焦らせたりせず、本人のペースに合わせて温かく寄り添う姿勢です。声を出すことよりも、その人の存在や気持ちを肯定し続けることが、長期的な改善につながっていきます。